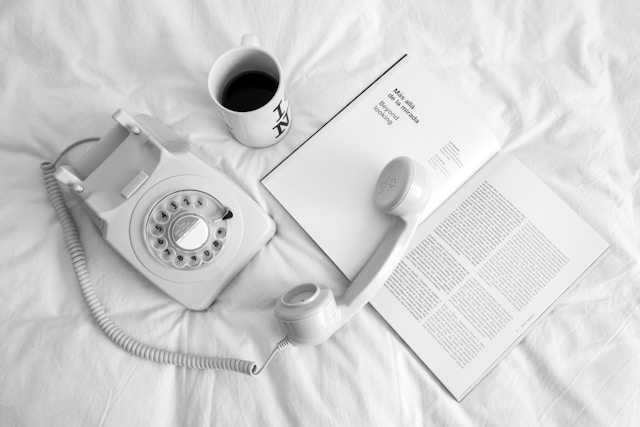
ウェブサイトの情報発信について
世界は複雑性は無限なのに、予算も時間も労力も有限
世界は複雑です。そのうえ雑然と混雑しています。
情報発信の根本的なむずかしさは、複雑性と混雑性の泡々のあいだを縫うようにして、届けるべき相手に届けることです。
理想論を言えば、あらゆるひとびとのあらゆる行動に最適化すべきです。つまり、メールしか見ないひとにはメールを送り、テレビしか見ないひとにはテレビCMをつくったり番組スポンサードを行ったり、ソーシャルゲームしかプレイしないひとにはゲーム内のオブジェクトに広告出稿したりゲーム関連イベントに協賛したり、あくまで理想論的にいろいろあるでしょう。
とはいえ予算も時間も労力も有限です。コストパフォーマンスもタイムパフォーマンスの観点は常に健在といえます。
そこで選ばれやすいのが「ホームページ」や「ウェブサイト」という情報発信の基地をつくることです。
弊社は、情報発信の基地としてのホームページを制作構築します。
ここでは、情報発信のノウハウについて手短に共有いたします。
情報の受け取り手が誰なのか極限までわかりやすい状態
情報発信において大事なことは山程ありますが、最初にお願いしているのは「ホームページに掲載する情報を受け取るべきひとが誰なのか極限までわかりやすい状態」にすることです。
情報が取捨選択されるとき、「じぶんのための情報ではない」と思われた瞬間に捨てられます。当然のことです。
受け取ってほしいひとに向けて「あなたのための情報です」と瞬時に、明確に、伝えなければなりません。
たとえば「今年高校二年生で、大学受験の志望校が決まらなくて、親からプレッシャーをかけられていてすこし焦っているあなたへ」とすれば、かなりわかりやすいです。あ、じぶんのことだ、となります。
whatではなくwhyを届ける
よっぽど理解のむずかしいものでないかぎり、「what」は見ればわかります。
たとえば、テレビ売り場で「いいテレビです、新しい型です、購入ポイントが付きます、ひとついかがですか」とスペックレベルのことを言われても、共感できる情報になりません。
一方で、「このテレビのブランドは、『映像クリエイターが作品に込めた想いのすべてを伝えたい』という想いで究極のテレビづくりに挑んでいます。その実現に向けて音と画面の一致、音に込められた感情の純粋な表現を追求し、ついにこのテレビが完成しました。おひとついかがですか」という情報に、人間は共感をするものです。
限られた時間のなかで、できるだけwhyを優先的に伝え、目に見えないもの曖昧な部分に共感してもらえるようにしたいです。
共感があると複雑性を越えていきやすい
情報発信には、「受け取ってもらうこと」と「受け取り続けてもらうこと」の二側面があり、どちらも一筋縄ではありません。
ただ、whyに共感してくれた受信者は、主体的に・自主的に・積極的に、じぶんから情報を引っ張りとってくれるようになるため、複雑性や混雑性を超えていきやすいです。
届けたい側が届けやすくなり、受け取りたい側が受け取りやすくなる、その最大のベネフィットのために「共感」を丁寧につくりこんでいく。
ここに労力をかける意義があります。
〈最小の負担で発信者のような精度で情報を受信してもらう〉ことを目指します。
言語的不安定度を軽減する
抽象的な観点で言えば、「言語的不安定度」(linguistic insecurity、リングィスティック・インセキュリティ)を軽減することが重要です。
言語的不安定度というのは、あることばに対してじぶんの思う意味や用途で合っているのか不安な度合いのことです。定義がわからない、用字がわからない、用途がわからない、みんなもおなじ意味で使っているのかわからない、そういう状態です。
たとえば、役所が「低所得者のためのサービスが始まりました」という件名で情報発信をしたとします。ここで「低所得者」とは誰のことなのか、つまりじぶんは含まれているのかわからない場合が多いです。
これが例えば封筒の送付で「送られてきた市民は全員対象」と添えてあればわかるでしょうし、ちょっと露骨な表示ですけど「年収240万円未満の市民のためのサービスが始まりました」でもいいですよね。
言語的不安定度が高いと、そもそも「じぶんのための情報だ」という受信への自信がなくなる(ピンとこなくなる)ため、届くべきひとに届かなくなる可能性が高まります。
継続的なプロセスの点検とデボトルネッキング こうした情報発信の落とし穴のようなものが、至るところにあります。それらをひとつひとつ見つけては取り除く地味な作業に毎日(ほんとうに毎日!)耐え続けなければなりません。
もしこれをウェブ担当者のかたが読んでくださっているとしたら、あなたか、あなたの部下がそういう人間でなければなりません。
たとえ成功した手法があったとしても、明日には使えなくなっていることがマーケティングではよくあります。なぜなら、お客さんやユーザーは毎日なにかを学び、刺激を受け、変わっているからです。
その切っ先に立ち、お客さんやユーザーのことをよく観察し続ける必要があります。 そしてまた課題があれば、デボトルネッキングして、様子を見る、という繰り返しです。いわゆる「OODAループ」(観察 observe → 方向づけ orient → 決定 decide → 実行 act)のような繰り返しの努力が必要不可欠です。
